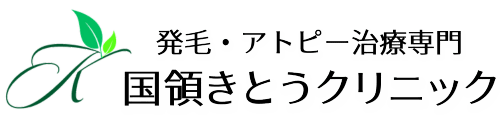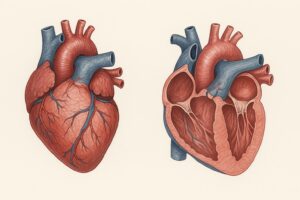人間の成人の安静時の心拍数は、1分間に60~100回とされていますが、平均的には60~70回で、85回以上は比較的まれです。
哺乳類では、ハツカネズミの心拍数は1分間に約600回位で寿命は2~3年、ネコの心拍数は1分間に約140回位で寿命は約10~15年、ゾウの心拍数は1分間に約30回で寿命は約70年越えと言われています。
つまり一般に心拍数が早い動物の寿命は短く、心拍数が遅い動物の寿命は長いといえます。
脈が速いと死亡リスクが高くなるとの研究報告がいくつもあります。
代表的なものに、岩手県大迫町(現在は花巻市)の追跡調査で、血圧が正常でも心拍数が1分間に70回以上の人はそうでない人よりも心臓病による死亡リスクが約2倍になる、という研究報告があります[ Hozawa A, et al. Am J Hypertens. 2004 17(11):1005-10]。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15533725
背景: 近年、家庭での血圧(BP)自己測定の利点が認識されつつある。同様の利点は、家庭血圧測定用に設計された機器を用いて家庭で測定された安静時心拍数(HR)値にも当てはまる可能性がある。しかし、家庭でのHR値が心血管疾患による死亡リスクを予測するかどうかを検討した研究はこれまで存在しない。そこで我々は、家庭で血圧と心拍数を自己測定できる機器を用いて、心血管疾患による死亡リスクの予測におけるHR値の有用性を検討した。
方法: 有意な不整脈のない40歳以上の日本人1780名を対象に、自宅で測定した安静時心拍数と10年間の心血管疾患死亡リスクとの関連を検討した。主要リスク因子を調整したCox比例ハザードモデルを用いた。
結果: 朝の家庭血圧測定値が5拍/分増加すると、心血管疾患による死亡リスクが17%上昇した(95%信頼区間5%~30%)。この関係は、家庭血圧値で調整した後でも統計的に有意であった。家庭血圧測定値の収縮期血圧が正常範囲(135mmHg未満)内であった場合でも、心拍数が70拍/分以上の被験者は、収縮期血圧と心拍数が正常であった被験者よりも心血管疾患による死亡リスクが高かった(相対ハザード比2.16、95%信頼区間1.21~3.85)。
結論: 自宅での心拍数の自己測定は、血圧の自己測定と併せて、心血管リスクを評価するための有用な臨床情報を提供する簡単な方法です。
様々な因子が原因として考えられ、一概に心拍数だけで寿命を予測できません。 しかしもともとあまり心拍数(脈数)が多くない方がかなり増えたら、夜ねている間も心臓はそれなりに動いている状態となります。 本来は休んで心臓も楽したいときに・・・
実際の測定に関しては起きている時に正確に心拍数を測るのは結構大変です。 クリニック,病院では当然緊張している場合が多いです。 緊張していないと思っていても実際の身体はかなりの緊張をしいられている,わけです。
アップルウオッチを最近はもっている方が増えました。 寝ている時の脈も測定できます。 「ミノキシジル」を服用されている方は一度ご確認をされた方がよいかもしれません。
ミノキシジルの内服は発毛にとても有効です。ですが、この薬は個人差がとても大きいです。
作用機序が完全に解明されていない事もありますが、心臓に負担がかかる場合がある事が一番問題となります。
遺伝が関係しているらしいのですが、ごく少量のミノキシジルでも心臓に水がたまる「心嚢液貯留」という状態が起こる事があります。 また脈が増えてしまう事がおおいです。
まったく問題ない方もたくさんいらっしゃると思います。 副作用の頻度は「多毛」という事象をのぞけば頻脈がかなり多いと思います。頻脈→血圧軽度低下→脈拍数増多→「動悸」が多いと思います。
若干の血圧低下がおそらく「めまい」「耳鳴り」「ふらつき」を起こしていると自分の体験上からは予想されます。
ミノキシジルを飲まれて何か症状が出現した場合は、その後仮に慣れてきて問題ないとしても 心臓の検査(心エコーなど)は受けた方が良い・・・というのは事実だと感じます。
上記の文献では70回/分以上・・・と記載があります。 これは個人差があります。
ミノキシジルを使用する前の心拍数の問題がからみます。 ですが、夜ねていて80回/分以上ある場合は多いかな? と自分なら思います。
ミノキシジルをいったん中止して5日くらい経過すれば(7日経過すれば十分)以前の心拍数になっていると思います。 起きている時の心拍数はいろいろな事に影響を受けます。 就寝中の心拍数の変化を確認してあまり多くなっている場合はミノキシジルの減量も検討した方が心臓の負担はすくないかもしれません。